はじめに:B型事業所の“工賃”をもっと豊かにするために
就労継続支援B型事業所(以下、B型事業所)では、利用者が働いた対価として「工賃(こうちん)」を受け取ります。
しかし全国的に見ると、その平均額は月15,000円前後にとどまっています。
「もっと利用者さんに還元したい」
「頑張った分をきちんと評価したい」
そう考えて日々取り組んでいる事業所も多いのではないでしょうか。
本記事では、全国のB型事業所が実践している工賃向上の取り組み事例5選を紹介します。
単なる数字の改善だけでなく、「働く意欲」や「笑顔」につながる工賃アップの方法を探っていきましょう。
第1章 B型事業所における“工賃”とは?
そもそも工賃とは?
B型事業所における工賃とは、利用者が生産活動などで得た利益の一部を分配する報酬です。
雇用契約に基づく「給与」ではなく、あくまで福祉サービスの中で支給される“成果報酬”にあたります。
- 作業量や参加日数によって支給額が変動
- 雇用保険・社会保険の対象外
- 事業所の生産性や販売力が大きく影響する
そのため、工賃を上げる=事業所の経営力を上げることにも直結します。
全国平均と現状の課題
厚生労働省の調査によると、令和5年度の全国平均工賃は約月17,000円。
10年前と比べると上昇していますが、まだ生活費を支えるには程遠い数字です。
課題としては、
- 受注作業に依存しすぎて利益率が低い
- 販売チャネルが限られている
- 生産性向上の仕組みが整っていない
- 利用者のやりがいが報酬に結びついていない
などが挙げられます。
それでは、実際に工賃アップを実現している事業所はどのような工夫をしているのでしょうか?
ここからは、成功事例5選を紹介します。
第2章 事例①:地域とつながる「地域連携型ビジネス」
● 地域の需要を取り込んで安定受注を実現
ある地方のB型事業所では、地元の飲食店や企業と協働し、
“地域限定の下請け業務”を請け負うことで工賃を大幅にアップしました。
例:
- 飲食店のテイクアウト用おしぼりの袋詰め
- 地元農家との提携で、青果の仕分け・出荷補助
- 商店街イベントでの清掃・設営
地域の小さな仕事を継続的に受けることで、
「利益率の高い軽作業」+「地域貢献」という好循環が生まれました。
💡ポイント
- 地域の商工会や自治体に積極的に相談する
- “定期性”のある仕事を受注する
- 「地域の戦力になる」という意識が利用者のやりがいにつながる
第3章 事例②:自社ブランドを立ち上げた「商品開発型」
● “福祉の製品”から“社会の製品”へ
全国で注目されているのが、自社オリジナル商品を開発して販売する事業所です。
例:
- 手作りクッキーやジャムなどの食品製造
- アート作品や雑貨の制作販売
- オリジナルロゴ入りの布製品・アクセサリー
中でもあるB型事業所では、利用者の描いた絵を商品化(ポーチ・Tシャツなど)し、
オンラインショップで販売。SNS発信によって注文が全国から届くようになりました。
結果、月平均工賃が2万円→4万円に上昇。
「自分の作品が誰かの手に届く」という経験が、利用者の誇りにつながっています。
💡ポイント
- “誰のために”作るかを意識した商品づくり
- SNSやECサイトを活用して販路を拡大
- 利用者の個性を「商品価値」に変える
第4章 事例③:企業との協働で“仕事の質”を上げる
● 民間企業とパートナーシップを結ぶ
ある都市部のB型事業所では、地元の物流会社と協働し、部品の検品・仕分け業務を受託。
企業と直接契約することで、安定した単価の仕事を得ることができました。
企業側にとっても、「安定した人材確保」「地域貢献」「CSR強化」につながるため、
“Win-Win”の関係が構築されています。
結果として、1人あたりの平均工賃は3万円台を突破。
利用者の社会的自立意識も高まりました。
💡ポイント
- 地元企業とのマッチングイベントに参加
- “丁寧で確実な作業”を強みにアピール
- 定期的に成果報告を行い、信頼を積み重ねる
第5章 事例④:デジタル技術を活用した「IT作業・デザイン支援」
● 在宅でもできる“新しい働き方”
デジタル技術を取り入れたB型事業所も増えています。
例:
- 名刺入力やデータ入力の受託作業
- チラシ・ポスター・WEBバナーのデザイン制作
- 動画編集やSNS運用サポート
「パソコンが得意」「クリエイティブな作業が好き」という利用者の個性を生かし、
高単価の仕事につなげているのが特徴です。
IT系の業務は、在宅でも対応できるため、体調の波がある利用者にも適しています。
💡ポイント
- 無料ツール(Canva・Google Workspaceなど)を活用
- スキル習得の時間を“作業の一環”として評価
- 成果物をポートフォリオ化して営業に活かす
第6章 事例⑤:「働く意欲」を高める“インセンティブ制度”
● 「頑張り」が“見える化”される仕組み
あるB型事業所では、作業量や姿勢を評価する独自のポイント制度を導入。
ポイントに応じて、
- 工賃ボーナス
- ギフトカード
- 表彰制度
などを設けたところ、利用者の意欲が大きく向上しました。
「頑張れば報われる」仕組みが、
モチベーションアップ → 生産性向上 → 工賃アップ
という好循環を生み出しています。
💡ポイント
- 評価は“結果”ではなく“努力”も含める
- 月ごとにフィードバックの機会を設ける
- 公平性よりも「成長の実感」を重視する
第7章 「毎日が夏休み。」の取り組み事例
就労継続支援B型事業所「毎日が夏休み。」でも、
工賃向上に向けた取り組みを積極的に行っています。
● ① 生産活動の多様化
- アクセサリー制作・雑貨販売・清掃業務などを組み合わせ、季節によって作業を変化。
- 一人ひとりの得意分野を生かす「選べる作業制度」を導入。
● ② SNS・ネット販売の強化
InstagramやBASEを活用し、利用者が作った作品を発信・販売。
「自分の作品が誰かに届く」経験が、やりがいと収益の両立につながっています。
● ③ チーム評価制度
個人評価だけでなく、チーム単位で成果を共有。
「みんなで頑張る文化」が育ち、自然と工賃アップに結びついています。
理念: 人のために生きる
使命: 自分らしく、誠実な人の創造
価値観: 利他・自責・勇気・挑戦
利用者一人ひとりの成長が事業の成長につながる。
そんな支援を「毎日が夏休み。」は目指しています。
第8章 まとめ:工賃アップのカギは「人の笑顔」と「地域との共創」
工賃向上の取り組みは、単なる数字の改善ではありません。
その背景には、利用者のやりがい・地域とのつながり・支援員の情熱があります。
今回紹介した5つの事例に共通しているのは、
- 利用者の得意を生かしている
- 地域や企業と連携している
- 継続的に見直しを行っている
工賃を上げることは、“働くことの喜び”を届けること。
その努力の積み重ねが、利用者の笑顔と社会の理解を広げていくのです。
「工賃が上がる」=「人が輝く」
それが、B型事業所の理想のかたちです。

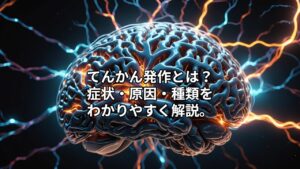
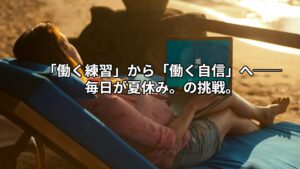
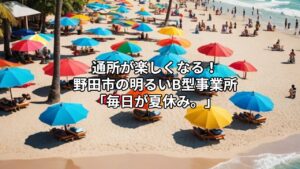
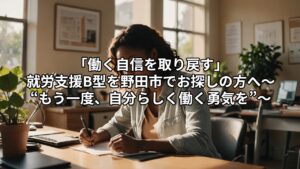


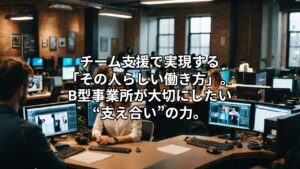

コメント