はじめに:「支援=指導」ではなく、「支援=寄り添い」
就労継続支援B型事業所(以下、B型事業所)の現場では、日々さまざまな利用者の方と関わりがあります。
障がいの種類も、性格も、人生の背景も、みんな違います。
そんな中で支援員に求められるのは、「教える力」ではなく「寄り添う力」です。
「どうしたら利用者が笑顔になれるのか」
「頑張れと言わずに、やる気を引き出すには?」
この記事では、「毎日が夏休み。」の支援員たちが実際に行っている、“笑顔を引き出す支援のコツ”を紹介します。
利用者の心に寄り添いながら、共に成長していく支援の在り方を一緒に考えていきましょう。
第1章 就労支援B型における「支援員」の役割とは?
“働く”を支える専門職
B型事業所の支援員は、利用者の「働く」「生活する」「つながる」を支える存在です。
単に作業を教えるだけではなく、“人生の伴走者”として寄り添う役割を担います。
支援員の主な業務は以下のとおりです。
- 作業支援(手順説明・サポート・見守り)
- 体調・メンタルの確認
- 生活面の相談支援
- 就労に向けた目標設定と振り返り
- 家族・関係機関との連携
利用者が“安心して挑戦できる環境”を整えることが、支援員の最大の使命です。
支援の本質は「相手の中に答えがある」と信じること
支援員の中には、最初「こうした方がいい」「こうすればできる」と“指導”の形で関わってしまう人もいます。
しかし、それでは利用者が「やらされている」感覚になり、笑顔は生まれません。
本当に大切なのは、相手の中に答えがあると信じること。
支援員の役目は“答えを与えること”ではなく、“一緒に見つけること”です。
第2章 支援員が大切にする3つの基本姿勢
姿勢①:観察する(見る支援)
「支援は“言葉”より“観察”から始まる」
これは、経験豊富な支援員がよく口にする言葉です。
利用者の表情、作業スピード、声のトーン、体の動き──。
一見小さな変化に気づけるかどうかが、信頼関係の第一歩です。
例:「今日は少し顔色が悪い」「作業の手が止まっている」
→「どうかしましたか?」と声をかけるだけで、心がほどけることがあります。
“見る”という姿勢が、安心をつくります。
姿勢②:受け止める(聴く支援)
利用者の言葉を「否定せずに聴く」こと。
これが、笑顔を生む最もシンプルで、最も難しい支援です。
「できない」
「疲れた」
「行きたくない」
そんな言葉にも、「この人はサボっている」ではなく、
「それほど頑張ってきたんだな」と受け止めることが大切です。
支援員が“聴く”姿勢を持つことで、利用者は「この人は自分を分かってくれる」と安心し、
心を開き始めます。
姿勢③:信じる(待つ支援)
支援現場では、「もっとできるはず」「頑張ってほしい」と思う場面も多いでしょう。
しかし、支援員が焦ってしまうと、利用者も苦しくなります。
支援のコツは、「信じて待つ勇気」を持つこと。
「今日はできなかったけど、明日はできるかもしれない」
「きっと、この人なりのペースで前に進んでいる」
信じて待つことが、利用者の“自分でやってみよう”という力を引き出します。
第3章 笑顔を引き出す支援の実践ポイント
「できた!」を一緒に喜ぶ
利用者が笑顔になる瞬間の多くは、「自分の力で何かをやり遂げたとき」です。
例:「今日は最後まで集中できた」
「昨日より早く作業ができた」
「自分で片付けができた」
その小さな成功を、支援員が一緒に喜ぶことが大切です。
「できて当たり前」ではなく、「できたね!」と素直に言葉にする。
それだけで、利用者の表情は明るくなります。
「否定しない」より、「承認する」
支援現場では、「怒らない」「叱らない」は意識しやすいですが、
それだけでは笑顔は生まれません。
重要なのは、「認める」こと。
「今日も通えたね」
「昨日より早く来れたね」
「そのやり方、いいね!」
承認は、利用者に“自分を肯定する力”を育てます。
承認の積み重ねが、やる気と笑顔の土台になるのです。
「その人らしさ」を活かす
B型事業所の利用者には、それぞれ個性や得意分野があります。
- 細かい作業が得意な人
- 話しかけるのが上手な人
- 音楽を聴くと集中できる人
支援員の役割は、「苦手を直す」よりも「得意を伸ばす」ことです。
「あなたのやり方でいいよ」と言える支援が、笑顔を生む最大の秘訣です。
第4章 事例紹介:「毎日が夏休み。」の支援現場から
ケース①:「話しかけても反応がなかった方が、今では冗談を言うように」
最初の頃、まったく会話をしなかった利用者さんがいました。
しかし、スタッフが毎日「おはよう」「お疲れさま」と声をかけ続けて数か月。
ある日、「今日は眠いね」と本人の口から言葉が。
その瞬間、スタッフも涙が出そうになったそうです。
“何もしないようで、見守る支援”が信頼を育てるのです。
ケース②:「失敗して落ち込む利用者にかけた一言」
作業中にミスをして落ち込んでいた利用者さんに、支援員がこう声をかけました。
「失敗したっていいよ。今日は“新しい経験”をした日だね。」
その言葉をきっかけに、本人は少しずつ笑顔を取り戻しました。
B型の支援は、“できなかったこと”を責めず、“挑戦したこと”を褒めることから始まります。
ケース③:「“働くのが楽しい”と感じた瞬間」
ある利用者さんは、長い間「働くのが怖い」と話していました。
でも、毎日スタッフが「ありがとう」と声をかけ続けた結果、
ある日「働くのが楽しくなってきた」と笑顔で話してくれました。
この一言こそ、支援員にとって何よりのご褒美です。
第5章 支援員が大切にする“ラッキーマインド”の支援
「毎日が夏休み。」では、スタッフ全員が“ラッキーマインド”という考え方を共有しています。
「つらいときこそラッキー」
「失敗も次の成長のチャンス」
このポジティブな視点は、支援員自身の心を守るだけでなく、
利用者に安心と前向きさを届ける力になります。
支援員が笑顔でいること。
それこそが、利用者を笑顔にする最初の一歩です。
第6章 支援員に求められる“自己ケア”も大切
支援員自身が疲れていたり、焦っていたりすると、どんなに良い支援も続きません。
「毎日が夏休み。」では、スタッフ同士が感謝の言葉をかけ合い、支え合う文化があります。
「今日はありがとう」「助かったよ」
この小さな声かけが、支援員の心を温かく保ち、結果的に利用者の笑顔につながります。
“支援する人が幸せであること”──それが本当の支援の基礎です。
第7章 まとめ:「笑顔を生む支援」は、“小さな優しさ”の積み重ね
利用者が笑顔になる支援とは、特別な技術ではありません。
日々の小さな気づき、声かけ、承認の積み重ねです。
- 無理をさせない
- 否定しない
- 一緒に喜ぶ
- そして、信じて待つ
この4つの姿勢があれば、必ず笑顔は生まれます。
「毎日が夏休み。」の支援員たちは今日も、
“誰かの一日を少し明るくする支援”を続けています。
「あなたが笑うと、私も嬉しい」──その想いが、すべての支援の原点です。

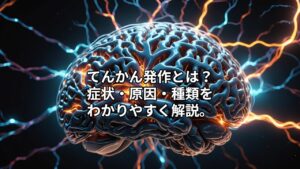
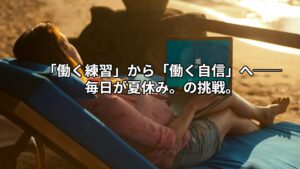
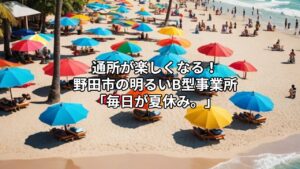
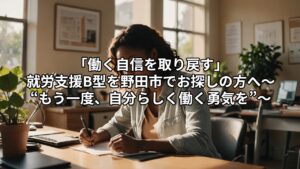


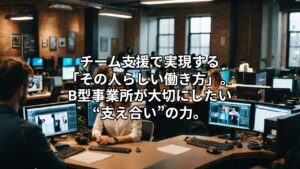

コメント