はじめに:「やる気が出ない」は責めるべきことではない
就労継続支援B型事業所(以下、B型事業所)では、
「やる気が続かない」「集中できない」「行動に移せない」といった悩みを抱える利用者が少なくありません。
しかし、“やる気が出ない”のは本人の怠けではなく、心の状態や環境の影響によるものです。
そんな時に役立つのが、心理学の視点です。
支援員が少し心理的な理解を持つだけで、利用者のモチベーションは驚くほど変化します。
本記事では、障がい福祉の現場で実践できる「心理学的アプローチ」を使ったモチベーション支援の方法を解説します。
第1章 モチベーションとは?福祉支援における“やる気”の正体
「モチベーション=内側のエネルギー」
モチベーションとは、人が行動を起こすための心理的なエネルギーのことです。
B型事業所の現場では、このエネルギーが「作業に取り組む意欲」や「通所の継続力」として表れます。
「頑張りたいけど体が動かない」
「どうせ自分には無理」
こうした“心のブレーキ”を外すには、外側からの声かけよりも、内側の動機づけを高めることが大切です。
モチベーションには2種類ある
心理学では、モチベーションは大きく2つに分かれます。
| 種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 外発的動機づけ | 報酬・評価・褒め言葉など外からの刺激で動く | 「工賃がもらえるから頑張る」 |
| 内発的動機づけ | 興味・楽しさ・達成感など自分の内面から動く | 「この作業、楽しい」「できるようになりたい」 |
B型事業所の支援では、外発的動機づけをきっかけに、内発的動機づけへとつなげていくことが理想です。
第2章 心理学が教える「やる気を引き出す」3つの原則
原則①:自己決定理論 ―「自分で選ぶ」ことがやる気を生む
アメリカの心理学者デシとライアンが提唱した「自己決定理論」では、
人のモチベーションは次の3つの欲求が満たされたときに高まるとされています。
- 自律性(自分で選びたい)
- 有能感(できたと感じたい)
- 関係性(誰かとつながっていたい)
たとえば、B型事業所で支援員が以下のような関わりを意識するだけで、
利用者の行動意欲は自然と上がります。
| 欲求 | 支援のポイント |
|---|---|
| 自律性 | 作業を「選べる」「決められる」機会を増やす |
| 有能感 | 「できた」を具体的に言葉で伝える |
| 関係性 | 一緒に喜び、一緒に笑う時間を作る |
「あなたが決めたことを応援するよ」
この一言が、“やらされている支援”から“自分で動く支援”へ変えるきっかけになります。
原則②:ピグマリオン効果 ― 期待は人を成長させる
ピグマリオン効果とは、他者からの期待が成果を高める心理効果のことです。
B型事業所の現場では、
「あなたならできると思うよ」という一言が、
利用者の行動を変える大きな力になります。
支援員が心から「信じている」姿勢を示すことで、
利用者は「自分もやってみよう」と思えるようになります。
ただし、過剰な期待は逆効果になることも。
“現実的で、温かい期待”がモチベーションを支える鍵です。
原則③:スモールステップ理論 ― 小さな成功を積み重ねる
アメリカの心理学者スキナーが提唱した「行動分析学」では、
人は“成功体験の積み重ね”によって意欲を維持するとされています。
「昨日より5分長く作業できた」
「1週間休まず通所できた」
このような“小さな達成”を見逃さずに承認することで、
「やればできる」という感覚(自己効力感)が育ちます。
支援員は、“100点を目指す支援”ではなく、
“1歩を認める支援”を心がけましょう。
第3章 現場で使える心理学的アプローチ5選
① リフレーミング(Reframing)
物事の見方を変えることで前向きに捉える方法。
例:
「失敗ばかりしている」→「それだけ挑戦している」
「作業が遅い」→「丁寧にできている」
支援員の言葉一つで、利用者の自己評価が変わります。
② モデリング(Modeling)
他の人の行動を見て学ぶ心理効果。
支援員や仲間の行動が「やってみよう」というきっかけになります。
例:
- 支援員が作業の手本を見せる
- 他の利用者の成功体験を共有する
③ フィードバックの工夫
指摘や評価をするときは、
「できている点 → 改善点 →励まし」の順で伝えると効果的です。
例:
「昨日より集中できていましたね(承認)」
「少し疲れたら休憩しても大丈夫ですよ(助言)」
「次も自分のペースでやってみましょう(励まし)」
④ 目標設定理論(Goal Setting Theory)
「何を目指すのか」を明確にすることで行動が継続しやすくなります。
ただし、目標は“できる範囲で具体的”に設定することがポイント。
✗「頑張る」
〇「今週は3日通う」
〇「今日は作業を30分続けてみる」
達成できる目標が“成功の連鎖”を生みます。
⑤ ポジティブ心理学
心理学者セリグマンが提唱した「強みに注目する考え方」。
「できないこと」ではなく「できること」「得意なこと」に焦点を当てます。
B型事業所では、
- 手先が器用 → 製作作業を担当
- コミュニケーションが得意 → 清掃や接客を担当
など、“強みを活かす配置”がモチベーション向上に直結します。
第4章 「毎日が夏休み。」で実践している心理支援の取り組み
就労継続支援B型事業所「毎日が夏休み。」では、
心理学の考えを日常の支援に取り入れています。
① ラッキーマインドの育成
「つらい時こそラッキー」「失敗も経験の一部」と考える“ラッキーマインド”をスタッフ全員で共有。
支援員自身が前向きでいることで、利用者の安心感も高まります。
② WOOP法を活用した目標支援
心理学的目標達成法“WOOP”(Wish/Outcome/Obstacle/Plan)を用いて、
利用者と一緒に「現実的で前向きな計画」を立てています。
例:
Wish:週3日通いたい
Outcome:生活リズムが整う
Obstacle:朝起きられない
Plan:支援員が朝電話をかけてサポート
③ “できたこと日報”で自己肯定感アップ
作業後に「今日できたこと」を1つ書く習慣を導入。
「少しずつ前に進んでいる」という実感を積み重ねる仕組みです。
④ チーム支援の導入
心理的安全性を重視し、スタッフ全員が声かけ・承認・共有を行う体制を整備。
「誰か1人が支える」のではなく、「チームで支える」文化が定着しています。
第5章 支援員が知っておきたい“心理的関わり方”の心得
1. 否定しない
「できない」も「今はできない」と捉える。
否定せず受け止める姿勢が信頼を育てます。
2. 期待を伝える
「きっとできる」「あなたなら大丈夫」──この言葉は行動のエネルギーになります。
3. 共に喜ぶ
成功の瞬間を一緒に喜ぶことで、「またやってみよう」という気持ちが生まれます。
4. 支援員自身も笑顔でいる
支援員の表情は利用者の心理状態を映す鏡。
笑顔でいるだけで安心と前向きさを届けられます。
第6章 まとめ:心理学は“心の福祉”を支えるもう一つの柱
モチベーションは、「本人のやる気」ではなく「環境が育てるもの」。
支援員が心理学的な視点を持ち、声かけや関わり方を少し変えるだけで、
利用者の行動も表情も変わります。
「働きたいけど怖い」
「自信がない」
そんな気持ちを抱く人に、
“あなたにはできる力がある”と信じること。
それこそが、福祉現場での心理支援の原点です。
「毎日が夏休み。」は、心理学を活かした支援で、
一人ひとりが“自分らしく働く喜び”を感じられる社会を目指しています。
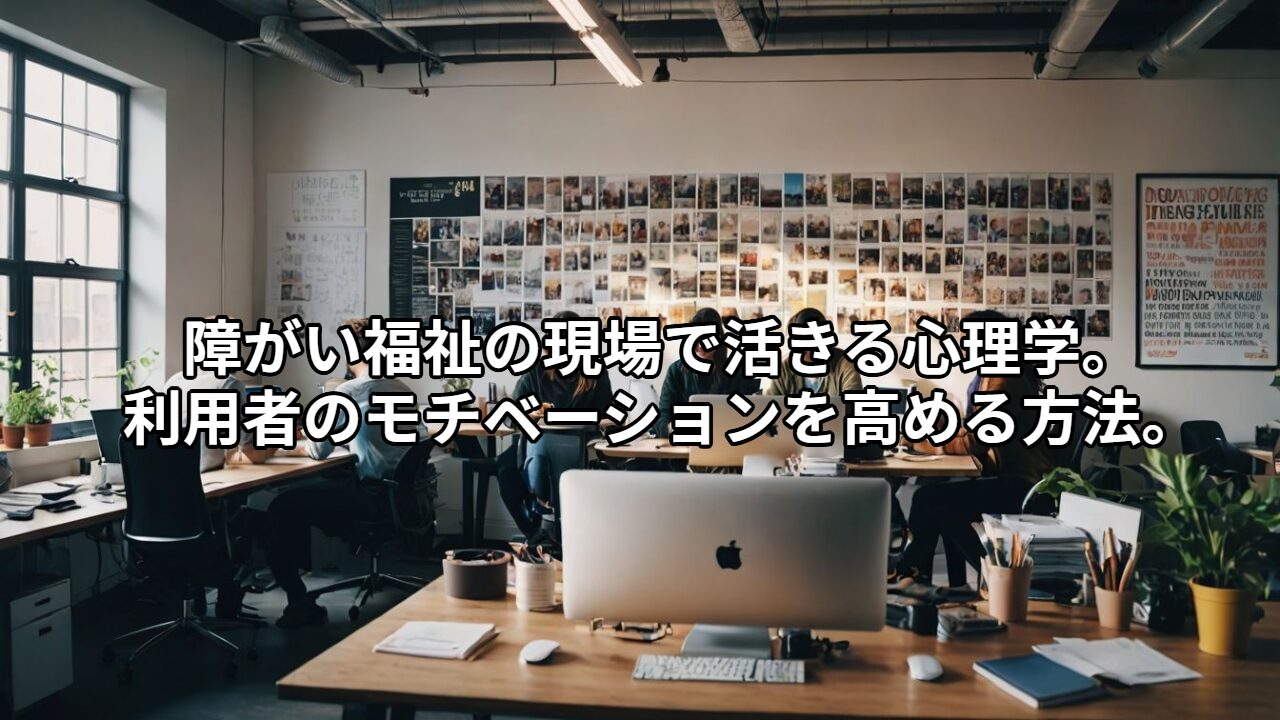
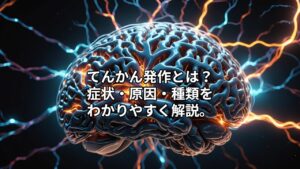
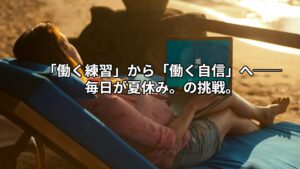
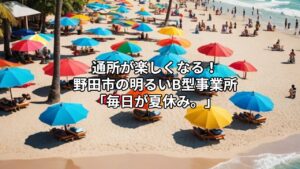
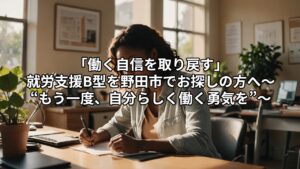


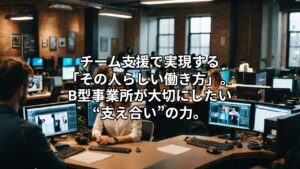
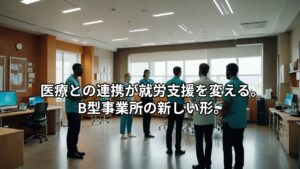
コメント