はじめに:「支援員一人の力では支えきれない」からこそ、チームで
就労継続支援B型事業所(以下、B型事業所)の現場では、日々多様な利用者が通所しています。
精神障がい、発達障がい、身体障がい、知的障がいなど、障がいの特性も、生活背景も、得意・苦手もそれぞれ違います。
そんな利用者一人ひとりに「その人らしい働き方」を提供するために欠かせないのが、“チーム支援”です。
支援員一人の力で支えられることには限界があります。
複数の職員が知恵を出し合い、連携し、利用者と一緒に課題を解決していくことで、
「誰かに任せる支援」から「みんなで支える支援」へと変わっていきます。
本記事では、B型事業所におけるチーム支援の考え方と、実践のポイント、そして利用者の“自分らしい働き方”を実現するための仕組みを紹介します。
第1章 なぜ今、B型事業所に“チーム支援”が必要なのか
一人で抱え込む支援の限界
福祉の現場では、「支援員Aさんが担当だから」という形で一人の職員に負担が集中しがちです。
しかし、支援は人の心と生活に関わるもの。
- 利用者との相性
- 状況判断の難しさ
- 感情労働による疲弊
こうした課題を、一人で抱え込むと支援の質が下がり、利用者の変化にも気づきにくくなります。
「支援員が孤立する支援」から、「チームで支える支援」へ──。
この変化が、利用者の安心にも、スタッフの働きやすさにもつながります。
チーム支援の本質とは?
チーム支援とは、複数の視点と専門性を活かして、一人の利用者を多面的に支える支援体制のことです。
単に「情報共有する」だけではなく、
- 状況の理解を共有し
- 支援方針を協働で決め
- 実践を分担して行う
この流れが“真のチーム支援”です。
支援員、サービス管理責任者、生活支援員、看護師、家族、医療機関──
それぞれが“その人の人生の伴走者”として関わることが、支援の深さを生み出します。
第2章 チーム支援で生まれる3つのメリット
メリット①:利用者の変化に気づきやすくなる
人は毎日少しずつ変わっていきます。
「今日はいつもより元気」「作業の集中力が上がった」など、
小さな変化を複数の職員で観察・共有することで、早期対応が可能になります。
「Aさん、最近休みが減ってきましたね」
「昨日の会話で、自分から“働くのが楽しい”って言ってましたよ」
こうした声の積み重ねが、利用者の成長を支える“気づきの連鎖”になります。
メリット②:支援方針のズレが減る
支援員ごとに関わり方や言葉の使い方が違うと、利用者が混乱してしまうことがあります。
チームで支援方針を共有することで、「伝え方」「目標」「ペース」を統一できます。
「できない」ではなく「一緒にやろう」
「頑張って」ではなく「今日もよく来たね」
言葉のトーンまで共有することで、支援が一貫し、利用者の安心感が増します。
メリット③:スタッフ同士の安心感・学びが広がる
チームで支援を行うことは、職員自身の成長にもつながります。
他の支援員の対応を見て学び、互いに相談し合える環境は、バーンアウト(燃え尽き)を防ぐ効果もあります。
「自分の支援スタイルを見直すきっかけになった」
「一人で悩まずにすむようになった」
支援の質だけでなく、職員の心の健康を守ることもチーム支援の大きな役割です。
第3章 “その人らしい働き方”を支えるチーム支援の実践ステップ
ステップ①:情報共有の“仕組み”を整える
口頭だけの共有では漏れが出やすいため、
- 日誌・記録アプリ
- 朝礼・終礼での簡単報告
- 週1回のミーティング
など、定期的かつ簡潔な情報共有を仕組み化することが重要です。
「感じたこと」「気づいたこと」を記録する文化が、チーム支援の基盤です。
ステップ②:支援目標を“共通言語”で設定する
個別支援計画を作る際には、サービス管理責任者だけでなく、関わる全員で話し合うことが大切です。
- 本人の「やりたいこと」
- 家族の意向
- 医療・行政の意見
- 支援員の現場感覚
これらをまとめ、チームで一つの方向を共有することで、ブレのない支援ができます。
ステップ③:本人も“チームの一員”として関わる
忘れてはならないのは、利用者本人もチームの中心であるということ。
支援方針を一方的に決めるのではなく、
「あなたはどう思う?」
「どんな働き方が理想?」
と対話しながら決めていくことで、本人の主体性が生まれます。
この“共同意思決定”こそ、自己決定支援の本質です。
第4章 「毎日が夏休み。」が実践するチーム支援のかたち
就労継続支援B型事業所「毎日が夏休み。」では、
“チームで支えるからこそ、その人らしく働ける”という考えを大切にしています。
● ① 支援スタッフの連携体制
- サービス管理責任者が中心となり、週1回チームカンファレンスを実施
- 生活支援員・作業支援員・送迎担当・調理スタッフなど全員が意見を出し合う
- 情報はクラウド上で共有し、誰でも最新の状態を把握できるようにしている
● ② “強み”を活かす分担支援
「誰が得意か」に合わせて支援を分担。
コミュニケーションが得意なスタッフは会話支援、
観察力のあるスタッフは体調変化のチェックなど、
チーム全体で利用者を見守る体制を整えています。
● ③ “笑顔でつなぐ”ラッキーマインド文化
スタッフ全員が「つらい時こそラッキー」という前向きなマインドを共有。
落ち込む利用者にも自然と明るさを届けられるチーム風土が生まれています。
「誰かが笑顔なら、みんなが笑顔になれる」
それが、“毎日が夏休み。”流のチーム支援です。
第5章 利用者の声:「みんなで支えてくれるから安心できる」
「一人の職員さんだけじゃなく、みんなが自分のことを気にかけてくれている」
「気分が落ちた時でも、誰かが声をかけてくれるから通うのが怖くない」
「自分の意見を聞いてくれるのが嬉しい」
チーム支援は、利用者にとって“見守られている安心感”を生み出します。
誰かに頼るのではなく、誰と関わっても支援の質が変わらない──これが理想的なチーム支援の姿です。
第6章 チーム支援を成功させるための3つの心得
① 「他者を信頼する」
支援員同士で信頼がなければ、利用者の信頼も得られません。
「任せる」「頼る」勇気が、チームを強くします。
② 「情報はオープンに、批判はしない」
共有された情報を“責める材料”にせず、“改善の種”として受け止める姿勢を持ちましょう。
心理的安全性が高い職場は、支援の質も安定します。
③ 「利用者を中心に置く」
「自分のやり方」や「事業所の都合」ではなく、
常に「この人にとって最善か?」を軸に支援方針を話し合うこと。
その視点が、チーム全体を一つにします。
第7章 まとめ:チームで支えるからこそ、ひとりの“らしさ”が輝く
支援とは、ひとりの力で完結するものではありません。
支援員、仲間、医療機関、家族、地域──すべての人がチームになって初めて、
利用者は“自分らしく働く力”を取り戻していきます。
「その人らしい働き方」とは、
一人の支援ではなく、“みんなの支援”が作るもの。
就労支援B型事業所「毎日が夏休み。」は、これからもチーム支援を通じて、
利用者一人ひとりが笑顔で働ける社会を目指します。
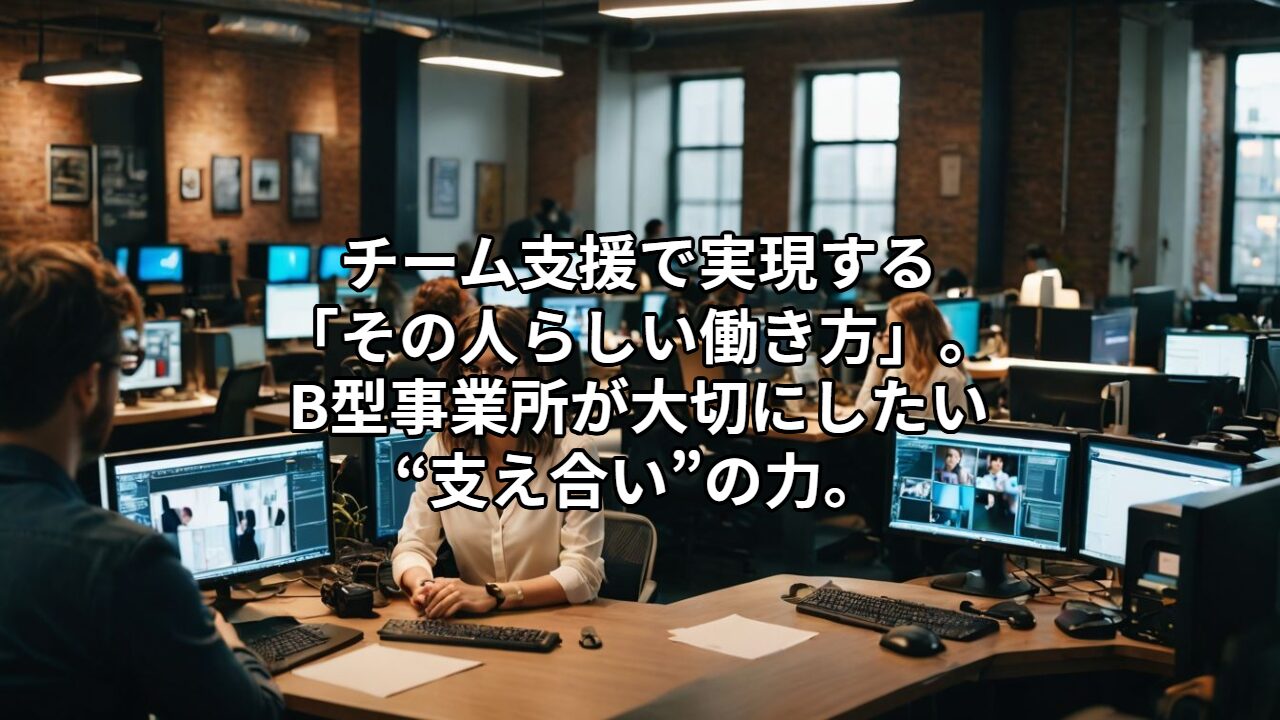
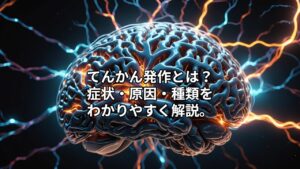
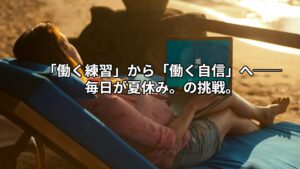
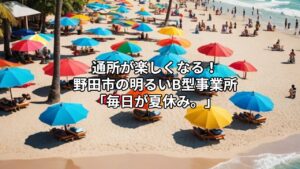
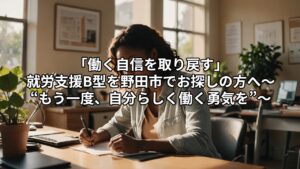



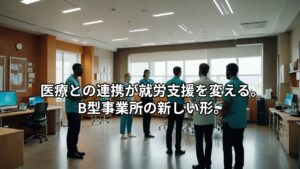
コメント